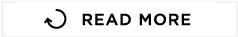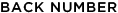こんにちは。ハバナトレーナーズの石原です。少々前回のコラムから時間が空いてしまいましたが、その分今回は濃い内容でお送りさせて頂きます!さて、前回に引き続き、ゴルフの指導現場でご活躍されているプロへの取材コラムです。
今回は、オンワードゴルフアカデミーさんにお邪魔してまいりました。二子玉川駅からアクセスも良く、設備も素晴らしいこちらのアカデミーに所属されている向江寛尚プロに、現場でのイップスについてのお話を伺うことができました。
非常に参考になるお話が盛りだくさんでしたので、早速取材の模様をお送りさせて頂きます。

石原「お忙しい中、貴重なお時間を下さりありがとうございます。早速ではございますが、プロはイップスに悩む生徒さん数多く見てこられたとお聞きしましたが、具体的にどんな症状の方がいらっしゃいましたか?」
向江プロ「たくさんいらっしゃいますよ。とある方は、アドレスに入ったままクラブが動かなくなってしまう。なんとか思い切りバックスイングをとっても、カツーンとボールを勝ちあげるようにして、OBになってしまう。その方はマイホールです。ただ同じような症状でも、なぜか打てるホールがある方もいらっしゃいます。なんと言うか、ホールというよりも、ある一定の動きができないのでしょう。私が見てきたのはそんな症状です。ただ、イップスの定義というものが、いまいちわかりませんが。」
石原「そうなんです。イップスは未だ明確な定義がないのです。今から90年近く昔、1930年頃のゴルファー、トミーアーマーさんが、パターの際に手もとが震えて、まるでそれが「子犬の鳴き声(yips)のようだ」=yipsと名付けられただけで、90年間も多くの競技の選手たちを悩ませているにもかかわらず、いわば病名でなく「ニックネーム」のままなのです。だから、医療の現場でもどう扱っていいのかわからないのが現状です。」
向江プロ「ほ〜、そうなんですか。定義は不明確でも、ゴルフだけでなく、各スポーツで現象は一緒なんでしょうね。」
石原「一応、「自動化した動作の遂行障害」という定義は文献で使われているのですが、それではまだまだ「広すぎる」ように感じています。プロは、イップスの原因はどんなものだとお考えですか?」
向江プロ「やはり、「脳」からくるものでしょう。それから「視覚」。ゴルフを含めた多くのスポーツは、視覚から得た情報を動きに結びつけるということが重要です。ただ、ゴルフは視覚を遮断しての腕で判断して行わなきゃいけないときあるのです。視界からの情報を遮断すると、「空間認識」に頼って動作を行わなければならないのです。その辺りで認識にズレがあって起こってしまうのではないか、と考えています。」
石原「なるほど。スイングは早い動作ですから、確かに視界からの情報を処理していちいち動作を行なっていたら間に合わないですね。ちなみに、生徒さんには、その空間認識のズレは、どんな風に改善されるのでしょうか?」
向江プロ「おそらくヘッドとボールのコンタクトに意識が向きすぎていて、その空間認識間違えている時があるのだと考えています。そのため、そこに意識が向かないよう、違うことを考えてもらうように、という目的を持った上でドリル化して改善していきます。正しい空間認識を取り戻し、成功体験を積んでもらうことが重要だと思いますね。」
石原「具体的には、立ち位置を変えるなどでしょうか?」
向江プロ「立ち位置、というよりも、大切なのは重心とボールの位置関係を変える、というイメージです。イップスに悩む方は、小さい筋肉で捜査をしたがってしまう傾向があるので、いかに大きな筋肉を意識して動作を行うことができるかですね。」
石原「なるほど。重心とボールの正しい関係は、どのようなものでしょうか?」
向江プロ「重心の位置に対してボールが右にあると、右に重心が偏ります。反対に左にあると、左に偏る。ボールは、重心の近くに置いてあげることで、大きい筋肉を使ってスイングすることができるのではないか、と考えています。」
石原「確かに重心の位置が安定することで、イップス特有の過剰に指先に偏った意識から、嫌でも体全体、大きな筋肉を使った動作ができそうですね。すごく勉強になります!」
さて、向江プロへのイップス取材の前編はここまでになりますが、後編はさらにイップスの核心に迫った内容をお送りさせていただきます。私自身、目から鱗の視点で、イップス経験者でもある自分自身の症状にも、腑に落ちるお話ばかりでした。キーワードは、「脳が一番信頼している指は、どの指か?」です。
それでは、次回もお楽しみに!ありがとうございました!
 向江 寛尚プロ(1972年生まれ)
99年よりツアープレーヤーになる。その経験を活かし2005年からレッスンプロとして活動を開始。オンワードゴルフアカデミーのディレクターコーチを始め、プロ・アマ問わずにレッスンを展開している。テレビドラマなどでのゴルフシーンにおける監修も手がける。
向江 寛尚プロ(1972年生まれ)
99年よりツアープレーヤーになる。その経験を活かし2005年からレッスンプロとして活動を開始。オンワードゴルフアカデミーのディレクターコーチを始め、プロ・アマ問わずにレッスンを展開している。テレビドラマなどでのゴルフシーンにおける監修も手がける。
TEL 03-6411-7688

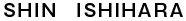 1982年群馬県生まれ。2007年早稲田大学スポーツ科学部卒業。現在、ハバナトレーナーズルーム恵比寿・代表。鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者(JATI-ATI)トレーナーとして、数多くのアスリートのトレーニング、コンディショニングをサポートする他、アスリートのフィジカルコンプレックスをなくすことを目指し、キューバスポーツ研究、イップス研究を行っている。また、柔道グランドスラム・キューバ代表サポート(2011年~)、ワールドベースボールクラシック2013・キューバ代表サポートなどの活動を行っている。
1982年群馬県生まれ。2007年早稲田大学スポーツ科学部卒業。現在、ハバナトレーナーズルーム恵比寿・代表。鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者(JATI-ATI)トレーナーとして、数多くのアスリートのトレーニング、コンディショニングをサポートする他、アスリートのフィジカルコンプレックスをなくすことを目指し、キューバスポーツ研究、イップス研究を行っている。また、柔道グランドスラム・キューバ代表サポート(2011年~)、ワールドベースボールクラシック2013・キューバ代表サポートなどの活動を行っている。著書『イップス スポーツ選手を悩ます謎の症状に挑む』(大修館書店)