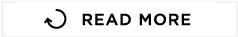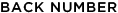こんにちは。ハバナトレーナーズルームの石原です。気候もすっかり暖かくなりましたね。私は、毎年この時期になると、何か新しいことを始めたくなってしまいます。実は私は、まだゴルフは練習場だけで、コースに出たことがないので、そろそろ本格的にゴルフを始めてみようかな、と思っています。野球でイップスを経験したので、「ゴルフでもイップスになるのではないか」とちょっと不安がありますが、自分で経験したら、イップス研究にも役に立つのではないかと思うので、頑張ってみようかと思っています。
さて、今回は、昨年半年間(全12回)に渡り、書かせていただきました「シーズン1」のコラムの最後に2回分でお送りさせて頂きました実践編のお話を振り返りたいと思います。(Season1-11はこちら、Season1-12はこちら)
イップスの症状は、いくつかのタイプに分類することができます。その分類の中で、まず大きく「動作を行う際は常に症状が出てしまうタイプ」と、「特定の状況でのみ症状が出てしまうタイプ」の二つに分類することができます。
シーズン1の実践編で、ご紹介したイップスに悩んでいるOさん。Oさんのカウンセリング内容から、Oさんは二つの分類のどちらに該当していたのかをもう一度、確認してみましょう。
イップスが起こる時の状況は
→ 負けたくない相手、認められたい人、知らない人がいる時
→ 細かな調整が必要な距離
→ それまでのショットがよく、バーディーが狙えそうな時
→ 逆にこれ以上「叩く」とスコアが自分の希望を上回りそうな時
実際にOさんに回答して頂いた、「そのまま」の内容がこちらです。裏を返せば、上に挙げた状況以外の時は、イップスの症状は出ずに、気持ちよくゴルフが出来るということになりますので、2つの分類のうち、後者の「特定の状況でのみ症状が出てしまうタイプ」であると考えることができます。
ちなみに、反対に前者の「動作を行う際は常に症状が出てしまうタイプ」の方に同じ質問をさせて頂くと、「『打とう』と思うと、体が固まったように動かなくなる」など、特定の場面を挙げずに回答されることが多いです。実際に、こちらのタイプの方だと、Oさんのように「楽しんでプレーできる時間」がないケースが多いため、クラブを握ること自体が嫌になってしまいがちです。その場合は、まず初めにOさんにご提案させて頂いた、「太いグリップ」を使うことで、動作を成功しやすくして、心理的なストレスを軽減することが最も有効な手段として考えられます。

しかし、Oさんのように特定の場面でイップスが出る方の場合には、症状の出る場面でのみ、動作の失敗を意識し、過剰な運動調節をしてしまうわけですから、症状の出ない状況で、太いグリップを使って練習してしまうと、実際のプレーで使うグリップを握った時に、相対的に細く、また手首、指先の自由度が高く感じてしまうため、イップスの症状を誘発し兼ねません。
そのため、実践編でOさんにもオススメしましたが、実際のグリップを握った時に安心感を感じるように、アドレスの直前まで、グリップよりも細い部分を握って、素振りなどを行い、実際のショットの際にグリップを握ることも、すぐに実践できる有効な手段としてオススメします。

ちなみにOさんには、イップスの機序の説明から、太さの違うグリップ使う意味などお話など、コラム読者の皆さまがイメージしやすいよう実験台も兼ねた実践編でしたので、太いグリップ、細いグリップ、両方実践させていただきましたが、感覚は過敏になっている状況で、間違えた取り組みをして失敗経験を重ねてしまうと、より動作遂行時に失敗を強く意識してしまう悪循環に陥ってしまうこともありますので、注意が必要です。
イップスって、やっぱり、謎が多い上に、難しいですね。(笑)
それではまた!

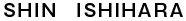 1982年群馬県生まれ。2007年早稲田大学スポーツ科学部卒業。現在、ハバナトレーナーズルーム恵比寿・代表。鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者(JATI-ATI)トレーナーとして、数多くのアスリートのトレーニング、コンディショニングをサポートする他、アスリートのフィジカルコンプレックスをなくすことを目指し、キューバスポーツ研究、イップス研究を行っている。また、柔道グランドスラム・キューバ代表サポート(2011年~)、ワールドベースボールクラシック2013・キューバ代表サポートなどの活動を行っている。
1982年群馬県生まれ。2007年早稲田大学スポーツ科学部卒業。現在、ハバナトレーナーズルーム恵比寿・代表。鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者(JATI-ATI)トレーナーとして、数多くのアスリートのトレーニング、コンディショニングをサポートする他、アスリートのフィジカルコンプレックスをなくすことを目指し、キューバスポーツ研究、イップス研究を行っている。また、柔道グランドスラム・キューバ代表サポート(2011年~)、ワールドベースボールクラシック2013・キューバ代表サポートなどの活動を行っている。著書『イップス スポーツ選手を悩ます謎の症状に挑む』(大修館書店)