『ゴルファーは眠れない』
山際淳司著 角川文庫(角川書店刊)

山際淳司さんという今は亡き作家を知っているだろうか?1980年に文藝春秋から創刊された『NUMBER』(創刊号のみNUMBER1)という雑誌で、「江夏の21球」というノンフィクションを書いて脚光を浴び、一躍スターライターになった人物である。そこには日本シリーズで登板したエース江夏の機微に渡る心理が克明に描き出されていた。
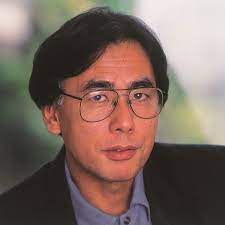
江夏本人に日本シリーズの映像を見せ、息を呑むような緊迫したシーンの中で、江夏は何を思って球を放ったのかを、山際さんが絶妙なインタビューで聞き出し、臨場感溢れる物語に仕立て上げた。その手法、その内容の面白さに、今もスポーツ好き、野球好きの中では語り継がれているスポーツノンフィクションである。
このようなスポーツマンの内面の葛藤を描いた文章はそれまで日本ではあまり見かけなかった。スポーツものと言えば新聞の報道文か雑誌のハウツーものだったのだ。しかし、アメリカではスポーツ選手を主人公とした読み物がすでに持てはやされていて、雑誌としては『Sports Illustrated』がこの世界をリードしていた。『NUMBER』はこの『スポイラ』と提携し、当時は『スポイラ』の記事を訳したものも多くあり、日本のスポーツファンには本場のスポーツを知る雑誌でもあった。
山際さんは創刊号のあとも野球を中心に続々とスポーツノンフィクションを書き続けた。乾いた文体といわれ、選手に感情移入することなく、選手心理を冷静に分析した読み物となっていた。こうしたことから山際さんは自らがスポーツマンであっただろうと思う人が多かったが、実はスポーツはほとんどやらなかった。『NUMBER』が創刊されるまで、フリーのライターとして人物ものを週刊誌に書いていた。私には『女性自身』では芸能人のインタビューをしていた記憶がある。ゴーストライトすることも多く、無名のライターだったと言っていい。

しかし、表だけでなく隠れた部分まで露わにしていく巧みなインタビュー術と筆致に『NUMBER』が目を留め、スポーツを書かせてみようと思ったのである。おそらく創刊号の編集長だった岡崎満義さんが巨体を揺すりながら、山際さんに白羽の矢を立てたのではないかと想像している。
「江夏の21球」が『NUMBER』創刊号に掲載された1980年、山際さんは32歳だった。仕事も覚え頑張りもきく年齢だった。その翌年の81年、私は大学を卒業して出版社に就職したばかりの駆け出しだった。そんな右も左もわからないときに、山際さんを知る会社の先輩から紹介を受けた。山際さんの本名は犬塚進。なので「ワンちゃん」と呼ばれていた。私は憧れのスターライターと突然会えたことで戸惑うもののとても嬉しかったことを覚えている。
それから5年くらい経った頃だろうか。私は勤めていた出版社をやめ、スポーツライターとして様々なスポーツを書き始めていた。そんな秋の日、ゴルフ雑誌社の依頼で試合のリポートを書くために、ゴルフコースの内側から選手の一挙手一投足をしゃがんで見つめていた私に、「ここで見てもいいかな」と言う人がいた。山際さんだった。私を覚えていてくれたことは嬉しく、並んで観戦した。しかし、山際さんが試合を観ただけで記者会見も出ずに帰ってしまったことは大きな疑問だった。
そしてその後、その試合での選手のことを山際さんが書いた文章を読み、選手の話も聞かずに原稿を書いてしまうのかと、ショックを受けた。つまり自分が思い描くストーリーに選手を当てはめた文章だったのだ。あの「江夏の21球」を書いたノンフィクションライターがなぜそんな安直なやり方で原稿を書くのかと。
あとでわかったことから言えば、この試合での山際さんは、すでにスポーツノンフィクションを書くことに飽きていたのかもしれなかった。もっと言えば嫌気がさしていたのかも知れない。それはいくら取材をしてもスポーツマンの真実など書けないと思ったからではないだろうか。所詮、他人のことはわからないと諦観したのかも知れない。
というのも、その後、山際さんは小説家に転身するからだ。これまでノンフィクションライターとして取材してきた事柄を題材にし、スポーツ小説を書き始めた。その小説は私を含め、山際さんのスポーツノンフィクションのファンからすれば迫真に迫るものがなく物足りないものに感じた。
軽いタッチの短編ばかりだったが、山際さんからすれば、小説は真実を書けないノンフィクションよりも、よっぽど自分にとっての真実であったのかもしれない。小説ならば嘘を書かなくて済み、嘘を書いて良く、より良い嘘が評価される虚構の世界なのだから。

私は山際さんの愛読者から離れていったが、山際さんのスポーツ小説は続々と刊行されていった。野球ものが多かったが、ゴルフものが何冊かある。その一つが今回紹介する『ゴルファーは眠れない』である。1992年に角川書店から単行本として刊行され、1995年に同出版社で文庫化されたものだ。
ゴルフの本を紹介するこのコラムを引き受けて、この本を読んでみたいと今さらながらに思ったのである。単行本の初版から30年が経つわけだが、とても面白く、新鮮な読み応えがあった。今の時代に合わせて多少の修正をすれば十分に新刊書として世に出せるものである。軽いタッチであることは若い頃に私が読んだ印象通りだったが、今となると山際さんをノンフィクションライターとしてではなく、小説家として受け入れることができる。そうなると、抵抗感がなく、すっと山際さんの小説が心に入ってきた。山際節が懐かしく快く感じられるのだ。
『ゴルファーは眠れない』は短編小説集である。6つの短編が収められているが、どれも洒落たタイトルが付けられている。登場人物の心理の綾を巧みに操り、1つの物語にまとめていく。世界的な短編の名手、オー・ヘンリーやトーマス・ハックスレー、フランク・オコナーらと互角に張り合えるストーリーテラーであると私には思える。
『ゴルファーは眠れない』に収められた1つめの短編は「オーバー・ザ・レインボー」で、ハワイのリゾートコースが舞台。この頃の私は『BAFFY』というゴルフ雑誌の編集長をしていて、毎年読者を連れてハワイの島々を巡ったことが思い出された。バブル経済が小説の背景に出てくるところも当時を偲ばせる。
2つめはタイトルとなった「ゴルファーは眠れない」。スコットランドの諺をモチーフとしたゴルフ好きの話。魅力的な女性とのアヴァンチュールを上手に絡めている。
3つめは「ゴルフ島奇譚」で、これはゴルフに取り憑かれた人の不思議な体験物語。日本のとある島に普通には見えないコースが存在し、謎を呼ぶ。ゴルフに神様はつきものという話でもある。
4つめは「葡萄畑にボギーマン」で、オーストラリアのパースを訪れた日本人ゴルファーの夢物語。パースは私も訪れたことがあるがコースに大きなカンガルーが何匹も戯れていたのが印象的だった。果たしてこの短編にカンガルーは登場するのか。
5つめは「サンドグリーンへ、ようこそ」。この短編もハワイが舞台だが、中東のコース設計家が芝と砂を組み替えた奇想天外のコースを造ろうとしているという話。女男や男女、ゲイなどが登場するのも、この時代ならではだ。
短編集の最後、6番目は「北の旅人」。視力を失いかけているツアーゴルファーと、恋人との生活を清算しようとする女性がゴルフコースで出会う。村上春樹の小説のような、喪失と再生がテーマとなっている。

山際さんはノンフィクションでも同様だったが、書き出しが巧みだ。意表を突く書き出しで即座に読者を惹きつける。さらには余韻を残すラスト。これから主人公はどうなっていくのかを読者に想像させる終わり方になる。これは短編の名手なら誰でも用いる手法だが、山際さんは雑誌での記事執筆でそのテクニックを身につけたに違いない。雑誌で鍛え上げた短めの文章で題材を面白くまとめ上げる力が、短編小説に存分に生かされている。
というわけで、ゴルフ好きの人で軽くゴルフのことを読んで見たいと思う人ならば、この『ゴルファーは眠れない』は恰好の1冊である。ゴルフをやりに遠出し、列車や飛行機のなかで時間を過ごすのにこれほどの本はないかも知れない。
ちなみに山際さんはこの文庫本が出版された1995年に進行性の胃癌で亡くなってしまった。46歳という若さだった。NHKの『サンデースポーツ』を降板した直後で、世間を驚かせた。私は山際さんの葬式にかつての会社の先輩たちと列席した。山際さんの遺影を見ながら、きっとまだまだ書きたかったに違いないと悲しくなったのを覚えている。
この『ゴルファーは眠れない』の文庫の後書きは小説家の赤川次郎さんが執筆しているが、あまりに早い山際さんの死を「あなたがいなくなっても、あなたの書いた本がいつまでも読み続けられるだろう」と悼んでいる。
最後に付け足したいのは、先に山際さんは小説家に転身したと私は書いたが、山際さんの経歴を今振り返ると、亡くなる間際までノンフィクションも書いていたようだ。とはいえ、その頃のノンフィクションを私は読んでおらず、その理由は先に書いた一件があったからだ。私としては山際さんがもしも長生きしていたら、ノンフィクション作家としてよりも小説家としてさらに名を挙げたように思える。長編も読みたかったものである。
文●本條強(武蔵丘短期大学客員教授)
※本書は1992年に角川書店で単行本となり、1995年に文庫本として刊行されました。どちらも古本で購入できます。






