『城山三郎 ゴルフの時間』 ゴルフダイジェスト社
人間の生き様を問い続けた気骨の作家が
ゴルフを生涯の友とした理由とは?
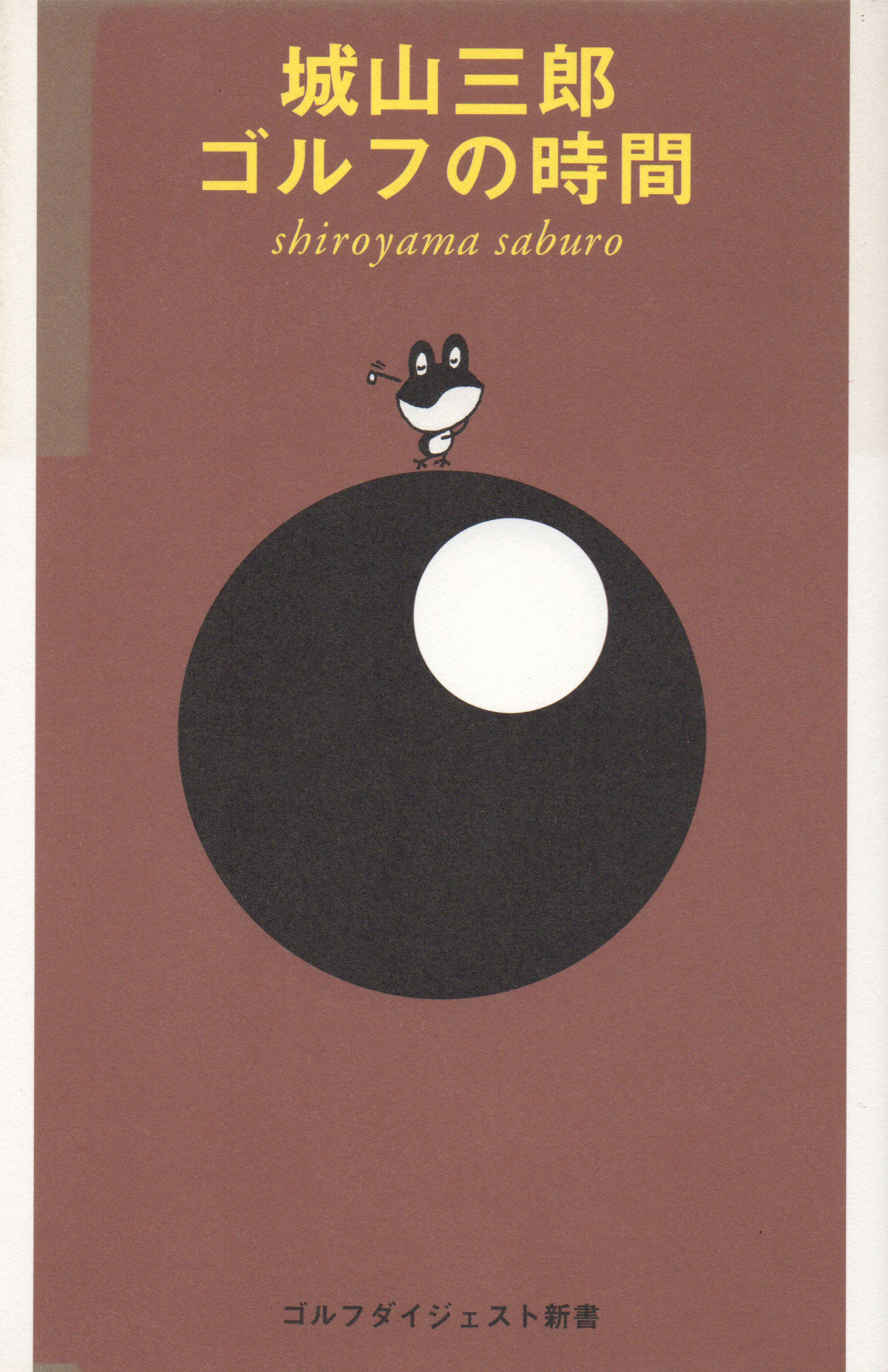
城山三郎は2007年、79歳で亡くなったが、今も尚、経済小説の大家として多くの著作が読まれている。年老いた大物総会屋を描いた『総会屋錦城』で直木賞を受賞したときから経済小説のエキスパートといわれた。伝記小説や歴史小説も手がけたが、どれも組織と個人の関係から人間の生き方を問い続けた。それは城山が何も知らぬ軍国少年だったことに起因する。
城山は1927年に名古屋市に生まれた。昭和2年生まれの軍国少年は徴兵猶予を返上して海軍の練習生となる。国家に命を託した少年だった。しかし、敗戦によって国の政治は軍国主義から一気に民主主義へと豹変する。昭和一桁の人の多くが国家に裏切られたと思ったように、城山も同様だった。大義がいとも簡単に変わってしまう世の中に強い疑問を抱いたのである。そしてその思いが小説『大義の末』に結実する。城山は書き終えた後、「死んでもいい」と思ったという。それほどの使命感を持って書いたものであり、城山文学の原点である。
なぜなら、城山の経済小説の多くは会社という組織の大義に押しつぶされまいとする一介のサラリーマンという個人の葛藤や苦悩を描いた作品だからである。つまり、会社という組織の大義は個人に優る、個人の犠牲の上に成り立ってもいいとする倫理が一般にまかり通っているからで、戦争体験者の城山はそこに疑問を抱き、メスを振るいたいという気持ちがあるのだ。城山の歴史小説や伝記小説も組織と個人の軋轢を描いたものがほとんどだ。
そうした思いは城山自身の生き方にもなっており、紫綬褒章も「国家がくれるものをありがとうございますと直に受け取れるか」と辞退している。城山が「気骨の作家」と呼ばれている由縁である。
城山の代表作としては先の1959年『総会屋錦城』『大義の末』の他、1963年『硫黄島に死す』があるほか、1966年鈴木商店焼き討ち事件を描いた『鼠』、1972年渋沢栄一を描いた『勇気堂々』、1974年廣田弘毅を描いた吉川英治文学賞受賞作の『落日燃ゆ』、1975年『官僚たちの夏』、1982年NHK大河ドラマとなった『黄金の日日』、さらに1988年オーガスタナショナルで日本人唯一のメンバーとなり、後に国鉄総裁になった『石田禮助の生涯』など枚挙に暇がない。まさに戦後日本の高度成長とバブル経済の功罪をしかと見てのものばかりで、どれも骨太の作品である。
こうした多忙な作家生活の中で城山の息抜きといえば、愛妻との旅行と好きな本を読む時間、そして友人や息子とのゴルフであった。

宮本留吉翁直伝の「トメ打ち打法」がもたらした変則打法
城山は随筆も数多く遺している。『打たれ強く生きる』『人生の流儀』『屈託なく生きる』『逆境を生きる』など、激動する世の中でどう自分らしく生きるか、不況の最中でもどう人生を楽しむかなど、城山の経験から若いサラリーマンなどに人生の処方を説いている。そして、人と知り合ったり楽しい時間を過ごすためにはゴルフが大変にいいというわけで、城山が自分のゴルフ経験を述べたものが、今回このコラムで紹介する『城山三郎 ゴルフの時間』である。
城山がゴルフを始めたのは39歳の頃。直木賞を取って7年目の頃で不眠症に悩まされ、そのため睡眠薬を多用していた。本人曰く、「ヒロポンと睡眠薬に頼っていた」で、催眠薬をウイスキーで飲むのだからどんどん痩せ細る。仕舞には錯乱状態に陥り、タンスに乗ったり鴨居にぶら下がったりと奇行を発症する始末。医者に診てもらうと「体が眠ることを忘れている」と言われて入院、「一日中体を使って疲れ果てて寝るようにしなさい」と忠告され、ゴルフを勧められて始めたのである。
最初はゴルフなど馬鹿馬鹿しいと思っていた城山も、文壇仲間に誘われて始めると爽快だし、疲れるしでゴルフが好きになる。何せ練習場へは2、3回程度行っただけですぐにコースに出て、広々とした大自然で遊べるのだから楽しいに決まっている。たとえボールに当たらなくとも、時々は当たる。柔道をやっていたから、体が戻ってきたら飛距離も出る。文壇のコンペにも参加して、腕を競うようにもなった。
当時、文壇ではゴルフをやらないヤツは病気になって死ぬと言われ、家に籠もりがちな作家はゴルフで健康になれと奨励されていたのだ。とはいえ、周りは明治大正生まれの大御所ばかり、昭和生まれの若い作家は石原慎太郎と城山くらいで、二人は良きライバルだった。とはいえ、城山のスイングは自己流であまりに酷い。
城山がゴルフを始めて2、3年経った頃、日本ゴルフ草創期に活躍した伝説のゴルファー、宮本留吉翁が城山のスイングを練習場で見てしまい、あまりのスイングの酷さから思わず教えることに。留吉プロが65歳の頃。ここで留吉プロが城山に伝授したのが「トメ打ち打法」、留めさんのトメ打ちである。
つまり、振り抜かずにインパクトでスイングを止めるというもの。「上からバーンと叩けば、球は上がる」がその教え。おそらく城山は球を上げようとしてすくい打ちになっていたのかもしれない。また、多くのアマチュアはすくい打ちが多く、球は飛ばず弱々しいものだから、「トメ打ち打法」はそれを矯正して強い打球が打てる良い打ち方だったのだ。
しかし、城山にとっては自分のスイングを根本から変える大改造であったため、簡単にはできなかった。できないから留吉翁はあれやこれやといろいろ教え出す。遂にはわけのわからぬ変則打法になってしまった。上から思い切り打ち込んで自爆するため、文壇仲間からは「特攻隊ゴルフ」と揶揄されていた。
その頃、文壇ゴルフは「PGA(ペンマンゴルフ協会)」と「青蕃会(アウトオブバーンズ会)」があったが、「PGA」の事務局長だった講談社の大久保房雄は城山のスイングを「パンタグラフ打法」と名付けていた。パンタグラフのように、トップで腕とクラブシャフトで作られる菱形が一度ひしゃげて、再び広げながらダウンスイングして打つから、その呼び名が付いた。息子の杉浦有一はそんな父のスイングを2段モーションだと言っているが、父は息子に大事なのはインパクトで、「それさえスクエならいいのだ」と諭していたという。
城山は当たれば飛んだが、変則打法故に安定しない。アプローチやパットなどの小物が上手でないのでスコアは「百獣の王」と本人が言うほど。茅ヶ崎に住んでいたため、近場の相模CCやスリーハンドレッドを根城にしていた。ゴルフを始めて5年経つ1977年当時のハンディキャップは26。おそらく生涯そうした実力だったようだ。しかしこれはOB続出の「青蕃会」からすれば並のスコアである。というのも、「青蕃会」の入会規則は「技倆拙劣」と「人格高潔」が条件だったからで、城山にはぴったりだった。
城山愛用のクラブは使う人の技倆に併せて翁自らが作った「宮本留吉モデル」。ドライバーなどウッドはパーシモンでアイアンはマッスルバック。シャフトはウッドもアイアンもスチールで、文壇仲間は体力が落ちてきた城山に「難しすぎるから替えろ」と忠告するも、「これがいいんだ」と生涯浮気せずに使い続けた。愛妻家の城山らしい一途さである。

大事な『無所属の時間』の時間を持つのにゴルフは最適である
健康のために始めたゴルフだから、スコアには頓着がなかった。せっかちな性分のため、さっさとボールに近づき、すぐに打つ。素振りをしないことも多かった。歩きながら打っていると評されたほどである。しかし、これは性分だけではなかったようだ。「他人に迷惑をかけない」が城山の信条だったからである。
スロープレーほどゴルフにおいて他人に迷惑をかけるものはないと思っていたのだ。だから、すぐに打つ。「塵もつもれば山となる」をもじって「チョロも積もればオンになる」などとうそぶいたが、下手だからこそ余計に早く打ったわけだし、何度か打ってグリーンに乗ればそれでよし。迷惑をかけずに済んだというわけである。まったく潔い。
それも「万年ブービーメーカー」と言いながらも、時たまは素晴らしいスコアであがる。知友の大平正芳元首相が亡くなって葬儀の日にゴルフコンペに参加した。城山にとってはおそらく形式的な葬式は好んでおらず、義理で来たような参列者を見るのは嫌だったのだろう。誰彼となく知人の葬式に日には、自分一人ひっそりと亡くなった人を思うことにしていたようだ。
このコンペでも「大平さん、大平さん」と唱えながら大平から贈られたパターを使ってみれば、パットがどんどん決まる。名門程ヶ谷CCで何と前半37、後半45のトータル82のベストスコアが出て優勝してしまったである。冥福を祈った城山に大平が天国から手助けしたのかもしれないが、立派なスコアである。
さらに城山は自分のモットーとして柔軟なものの考え方を好んでいた。ものをよく考え深く考察して、様々な選択があることを若者に知らせたかった。戦争の体験から盲目的に何かを信じる怖さを伝えたかった。サントリーの会長、鳥居道夫との対談でお互いにそのことに共感している。
発想の柔軟さが新しい商品を作る。失敗を恐れずに挑戦する。手間をかけることを惜しむと思考停止になって何も残らない。二者択一的な考えを止め、第3の道があることをいつも考える習慣づけをする。サントリーの佐治敬三社長の「やってみなはれ」の挑戦姿勢や鳥居道夫の「こんなもんや」の安易な取り組みはしないといった社訓にもつながっている。城山はこうしたことが人間を成長させ、楽しい生き方になると説いている。
城山にとってゴルフは楽しみであり、であれば楽しさを存分に味わう。ゴルフの楽しさは一緒に回る人をよく知ることができることにあると言って憚らない。根っからのいい人、明るい人、楽しい人ばかりではなく、底意地の悪い人、暗い人、面白みのない人もいるだろう。しかし、それらすべて城山にとっては興味津々の事柄である。何故にそんな人なのだろう、なんでそんな性格なのだろう、そうしたことを考えたり分析することが城山は好きなのである。人間に興味を抱く城山にとってゴルフは願ったり叶ったりのスポーツであり、それが作品に生かされるというわけである。
城山は60代に入ってから「残軀楽しまざるべけんや」という伊達正宗の言葉で生きていこうと思う。これは「今朝酒あらば今朝酒を楽しみ、明日憂来たらば明日憂えん」といった生き方である。もういい年になった。だったらくよくよせずに楽しくやろうよ。そういった生き方である。
城山は「人生の待ち時間は限られている。その中で時間を忘れるほどの陶酔をどれだけ多く持ったかで、人生の価値が決まるような気がする」と言い、これは「深く生きた記憶をどれほど残せるかで、人生は豊かなものになる」と説いている。城山は『かもめのジョナサン』を著したリチャード・バックの言葉も気に入っていた。それは「大変だったが、素晴らしかったといえる人生を送りたい」というものである。

そして、こうした豊かな時間は遊びではゴルフこそがもたらしてくれると城山は言い切る。それは「無所属の時間」でもあるという。どこにも属さずに縛られない自由な時間。そうした時間を人間は持たなければならず、それはゴルフが与えてくれたと言う。不眠症と睡眠薬で痩せ細った城山は「ゴルフで命拾いをした」と感謝していた。満足のいく作家活動ができたのも、ゴルフという余暇、「無所属の時間」を持てたからだというわけである。
この『城山三郎 ゴルフの時間』は先に記述したような、城山とサントリー会長の鳥井道夫や息子の杉浦有一(城山の本名は杉浦英一)との対談の他、川上哲治の息子、川上貴光との対談が収められているし、ゴルフダイジェストのコンペに参加したときにラウンドしながら話した事柄が掲載されている。
さらに城山がインタビューしたジャック・ニクラウスやトム・ワトソン、ジーン・リトラーのことや、経済人では五島昇や本田宗一郎との愉しいゴルフが語られている。政治家との交流も深く、先述した大平正芳他、宮沢喜一、中曽根康弘、岸信介などの話も出てくる。いずれも簡潔に書かれているので、もっともっと深く長く読みたいと思わせた。
城山は2007年に79歳で死去したが、その7年前に妻の容子を亡くした。彼女との長い結婚生活を『そうか、もうきみはいないのか』と題して随筆に纏めたものが死んだ翌年に出版され、田村正和主演でテレビドラマ化された。文人や出版人、ジャーナリストからも愛された人だった。
文●本條強(武蔵丘短期大学客員教授)
※本書は2007年に刊行されました。新刊はないため、amazon などで中古本が購入できます。






